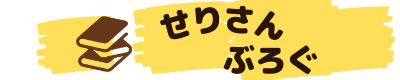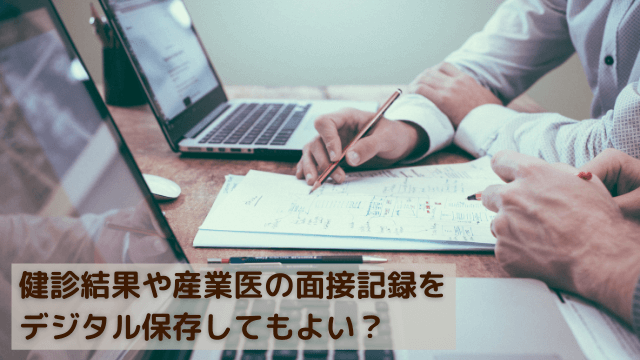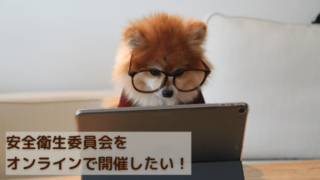※わかりやすく書き直しました。
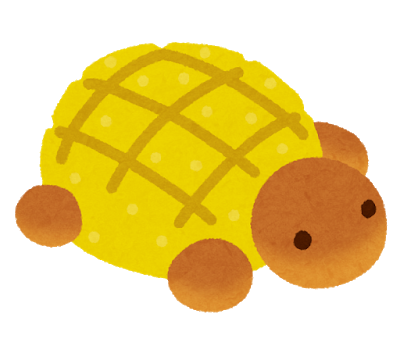
こんにちは!せりです。
健康診断やストレスチェック、長時間勤務者に対する面接指導結果などの文書保存に困っていませんか?
この記事では、事務職場における産業保健文書の
デジタル保存してもよいもの、デジタル保存の方法・期間について法令に基づいてわかりやすく解説します。
健康診断やストレスチェック、長時間勤務者に対する面接指導結果など、産業保健分野の文書は様々あり、保存場所や保存方法には頭を悩ませるところです。
紙をファイルに閉じて保存していると重いし、場所を取るし、結果の集計もめんどくさい。
エクセルなどのデータにしておけば集計も楽だし場所も取りません。最近は産業保健用の電子カルテシステムもいろいろと出ています。
でも、それで問題ないのでしょうか?
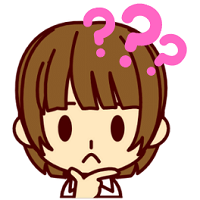
古い健康診断記結果や面接記録はまとめて捨ててもいいですか?
と聞かれることもありますが、安全衛生管理や産業保健に係る文書は保存年数が法令で決められているものが多いです。
知らずに捨ててしまわないよう、ぜひ最後までお読みください。
デジタル保存が認められている文書(事務職場関連)
電磁的記録によって保存してもよい文書は以下の通り
(注:ここに挙げているのは事務職場に関連する文書だけです)
- [3年間保存] 産業医による勧告内容と、それを踏まえて講じた措置の内容
- [3年間保存] (安全)衛生委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容、そのほか委員会に おける議事で重要なもの
- [5年間保存] 各種法定健康診断(雇入時、定期、特殊業務従事者、海外派遣労働者など)の個人票
- [5年間保存] 長時間勤務者に対する医師による面接指導の記録
- [5年間保存] ストレスチェックの結果
- [5年間保存] 高ストレス者に対する医師による面接指導の記録
- [3年間保存] 事務室内の作業環境測定の結果
- [3年間保存] 事務所の換気設備の点検結果
【厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令】第4条】より
(産業医による勧告等) 労働安全衛生規則 第14条の3第2項
事業者は、法第13条第5項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨 及びその理由)
※労働安全衛生法第13条第5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
(委員会の会議)労働安全衛生規則 第23条第4項
事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
(健康診断結果の記録の作成)労働安全衛生規則 第51条
事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票様式第五号を作成して、これを5年間保存しなければならない。
第43条(雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。(以下略)
第44条 (定期健康診断) 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下略)
第45条(特定業務従事者の健康診断) 事業者は、第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
第45条の2(海外派遣労働者の健康診断) 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
第46条 削除
第47条(給食従業員の検便) 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
第48条(歯科医師による健康診断) 事業者は、令第二十二条第三項の業務※に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断 を行なわなければならない。
※(筆者注)塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
労働安全衛生法 第66条第4項 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
(面接指導結果の記録の作成)労働安全衛生規則 第52条の6第1項 事業者は、法第66条の8の面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該法第66条の8の面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
労働安全衛生法 第66条の8 (面接指導等) 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
(労働者の同意の取得等)労働安全衛生規則 第52条の13第2項 ※ストレスチェックの結果
法第66条の10第2項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
安全衛生法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の 厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
(面接指導結果の記録の作成)労働安全衛生規則 第52条の18 ※ストレスチェック面接指導結果
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1 実施年月日 2 当該労働者の氏名 3 面接指導を行つた医師の氏名 4 労働安全衛生法第66条の10第5項の規定による医師の意見(※条文要約:遅滞なく意見聴取を行うこと)
(作業環境測定等)事務所衛生基準規則 第7条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第21条第5号の室について、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定しなければならない。
ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第2号及び第3号に掲げる事項については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
1 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 2 室温及び外気温 3 相対湿度
2 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
1 測定日時 2 測定方法 3 測定箇所 4 測定条件 5 測定結果 6 測定を実施した者の氏名 7 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
(点検等)事務所衛生基準規則 第9条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。
ちなみに、この記事に関連する文書のデジタル保存について定めた法令はこれです↓。

だいたいの文書はデジタル保存できるんですね。
保存方法については何か決められているのですか?
文書のデジタル保存はどこに?
省令によれば、デジタル文書の保存は以下の場所。
今時CD-ROMは使わない気もしますが、要するにパソコンにそのまま保存してもよいし、”これらに準ずる方法”として外付けHDでもUSBでもよいし、クラウドでもよいわけです。
「今まで紙で取っておいたけれどペーパーレスにしたい!」という場合にはスキャナで読み取って保存してもオッケー。
第四条(電磁的記録による保存)
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合ならびに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(以下略)
ただし、注意すべき点があります。
デジタル保存で注意すべき点
デジタル保存で注意すべき点は以下の通りです。
第四条(電磁的記録による保存)
4 民間事業者等が、第一各号又は第二項の規定に基づき別表第一の二若しくは四又は三の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。
二 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
三 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。
(以下略)
労基署の人が来た時などに、”きちんとした形式”の”書面”を速やかに出せるかどうかがポイントです。
保存期間中に書き換えがあってはまずいので、閲覧専用で保存するなどして、うっかり書き換えを防いでおくと安心です。もちろん、文書には作成者の氏名を入れます。
そして、バックアップをとること!これは必須です。
同じ文書を複数の事務所で保管する必要はある?
例えば、全従業員の健康診断結果を本社のサーバで保管していることってありますよね。
それぞれの支社でも、その支社ごとに従業員の健康診断結果を支社のパソコンやハードディスクなどにあらためて保管する必要があるのでしょうか?
それについては、 ”電磁的記録の保存” は本社でされていても、支社でパソコン画面などに表示でき、プリントアウトすることができるなら支社でも ”電磁的記録の保存” がなされているとみなすということになっています。
どうしてわざわざこんな条文があるのか気になったのですが、紙保存だったときには、本社で健康診断結果を全従業員分持っていたとしても、支社ごとに支社の従業員分のコピーを作って保管していたはずです。健康診断結果がないと健康管理ができませんから。
その感覚でこの条文を書いたのだと考えると納得です。
第四条(電磁的記録による保存)
5 別表第一の一の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存につき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(以下略)
まとめ
法令で保存が義務付けられている文書のうち、デジタル保存ができるものを紹介しました。
デジタル保存をするためには注意すべき点がいくつかありますが、特に難しいことはないように思います。
ただし、バックアップだけはくれぐれも忘れずに!!
(以前、文書を保存していたUSBが突然壊れて冷汗がでました)
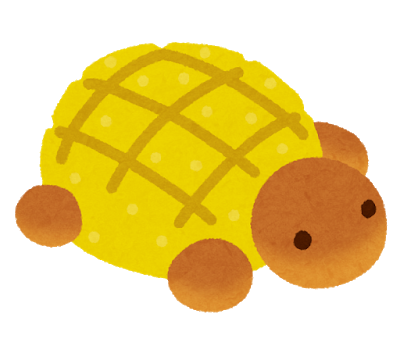
最後までお読みいただきありがとうございました!
文書の保存は年数が決まっていることがわかれば、あとは機械的に処分することもできます。
ただ、事業場によってはその人が退職するまで保存するところもあるかもしれませんね。
安全衛生委員会などで決めておくと安心です。
では、またお会いしましょう。