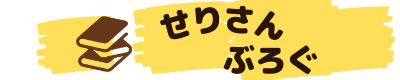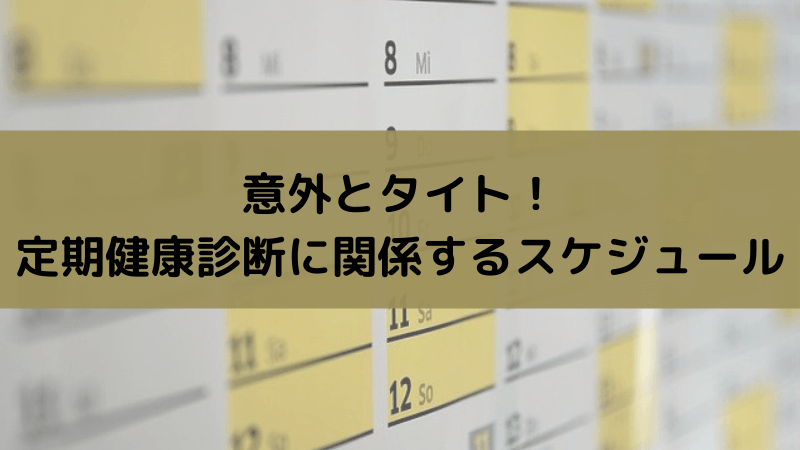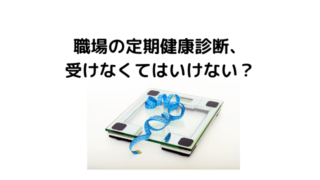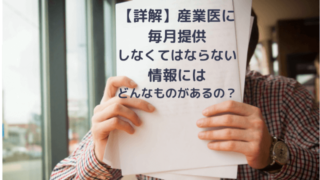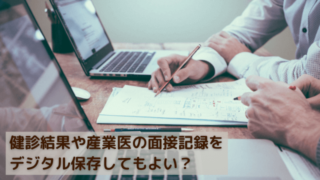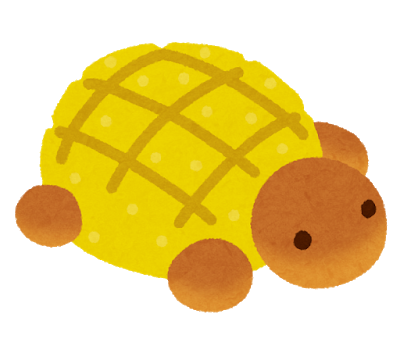
こんにちは!せりです。
この記事では、定期健康診断の一連の流れを、法令に定められた時間軸に着目してまとめました。
これを読めば定期健康診断のタイムスケジュールがつかめるようになります。
ぜひ最後までお読みください。
1年に1回行われる定期健康診断。
産業医は定期健康診断の結果を見て意見を述べたり、労基署に提出する「定期健康診断結果報告書」を確認したりしなくてはなりません。(印鑑はいりません。 ※過去記事「定期健康診断報告書等に押印がいらないってほんと?」参照)
しかし、事業場を訪問したときに職場巡視と面接で時間オーバーになってしまい、それらができなかった場合。いつまで先延ばししても大丈夫なのか心配になりますよね。
実は、定期健康診断の結果を個人に知らせるタイミングや結果を見て医師が意見を述べるタイミングなどは、法令で細かく決められています。これが意外とキツイ!
そこで、今回は定期健康診断に関連する作業を、根拠法令を示しながら時系列でまとめました。
根拠法令はいらないから結論だけ知りたい、という方は「まとめ」からお読みください。
定期健康診断の時期
定期健康診断を行う時期については、決まりはありません。ですから、1度に全員の定期健康診断を行っても、例えば誕生月に受診と決めて少しずつ行ってもよいのです。
ポイントは
対象となっている人(常時はたらいている人)が「1年以内ごとに1回、定期に」受けられるようにすること(労働安全衛生規則第44条)
ここさえ押さえておけば大丈夫です。
定期健康診断の周知・指導
定期健康診断の時期を決めたら、対象者がきちんと受診できるようにはたらきかけをします。
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 」 (以下「指針」)にはこう書かれています。
健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。
実は、定期健康診断は、事業者には実施の義務が、はたらく人には受診の義務があります(労働安全衛生法第66条第1項、第66条第5項)。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
(定期健康診断) 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下略)
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
とはいえ、はたらく人の大半は健康診断を職場が行う福利厚生の一環だと思っていて、自分に受診の義務があるなんて考えたこともありません。
こんなことを言われてしまうことはザラです。
ですから、職場からそれではダメですよ、とはたらく人に伝えて、対象者が健康診断をきちんと受けるようにしなくてはならないのです。
定期健康診断の結果の通知は1か月以内に
定期健康診断の結果は、2種類作成されます。
(注:常時はたらく人が50人未満の場合は1種類です)
- 受けた人ひとりひとりの結果が書いてある「個人票」
- 労働基準監督署に提出する「定期健康診断結果報告書」(常時はたらく人が50人以上の場合)
これらの結果は、健康診断を行ってからだいたい1か月以内に通知しなくてはなりません。
根拠法令等を見てみましょう。
個人票結果の通知時期 根拠
個人の健康診断結果の通知について、前述の 「指針 」にはこう書かれています。
事業者は、労働者が自ら健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるよう、労働安全衛生法第66条の6の規定に基づき、健康診断を受けた労働者に対して、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なくその結果を通知しなければならない。(強調筆者)
(健康診断の結果の通知) 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
※労働安全衛生法第66条の10は、ストレスチェックについての条文です
でました!「遅滞なく」
これは、これまでの法令解釈からも、概ね1か月以内ということで間違いなさそうです。
定期健康診断結果報告書の提出時期の根拠
そして、労基署に提出する定期健康診断結果報告書については、労働安全衛生規則にこう書かれています。
(健康診断結果報告)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (強調筆者)
こちらも「遅滞なく」!
とはいえ、労基署に提出する「健康診断結果報告書」は、定期健康診断の結果が全員分揃わないと作れません。
ですから、最後の人の結果が出てから1か月くらいのうちに出す、ということになると思います。
健康診断の結果について医師等からの意見聴取をする
職場の定期健康診断は、結果を個人に渡して終わり、というわけではありません。
健康診断の結果に異常が認められた人について「医師等の意見」を聞かなければならないんです(労働安全衛生法第66条の4)。
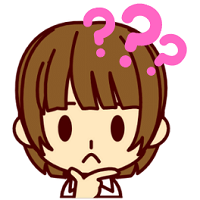
「医師等の意見」?
健康診断の結果には「異常なし」とか「要精密検査」とか書かれていますよね。あれのこと?
まぎらわしいのですが、それとは違います。
ここで言う「医師等の意見」は、異常所見があった人に対して
「通常勤務」「就業制限」「要休業」
など、その人がどのくらいはたらくことができるかという意見のことです(「就業区分」といいます)。
「医師等」って誰?とのことですが、 「指針」にはこのように書かれています。
産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である。(強調筆者)
そして、この意見を聴くのは定期健康診断を行った日から3ヶ月以内に行うこと(労働安全衛生規則第51条の2)とされていますが、
「指針 」にはこうも書かれています
事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく健康診断の個人票の様式中医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求めることとする。(中略)
また、意見の聴取は、速やかに行うことが望ましく(以下略)
(強調筆者)
出ました!「速やかに」。
「速やかに」ですと、おおむね2週間以内という解釈です(過去記事「【詳解】産業医に毎月提供しなくてはならない情報にはどんなものがあるの?」)。
労働安全衛生規則に3ヶ月って書いてあるけれど、どっちなの!?と困ってしまいますが、あくまで「望ましく」という表現なので、義務ではありませんが、早ければ早いに越したことはないということでしょう。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次の定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
医師等の意見は個人票に記入
医師の意見は、上の指針に書かれている通り健康診断の個人票に記載します。
個人票の様式は労働安全衛生規則第51条に「様式第5号」として示されていますが、これに記載されている項目を満たしていれば、どのようなレイアウトでもオッケーです。
(平成23年3月24日)(基安労発0324第2号)
健康診断個人票の様式については、安衛則第100条において、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであり、異なる様式を用いることを妨げるものではない
就業上の措置の決定
医師等の意見を聴いたら(個人票に記載されたら)、職場(事業者)はその意見に基づいて、就業上の措置を行うかどうか決定します。
例えば、医師が「就業制限が必要(残業禁止)」と意見を述べても、必ずしもそれをうのみにする必要はありません。
就業制限をするかどうか、するとしたら何をするかは職場(事業者)が決定します。
ただし、これを決めるときの注意点として「指針 」には就業制限を決める前に、はたらく人の意見も聞くこと、できれば産業医も同席して、みんなで納得のうえ就業制限を検討しましょう、と書かれています。
事業者は、(3)の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話し合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。
なお、産業医の選任義務のある事業場においては、必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意見を聴くことが適当である。
まとめ
- 定期健康診断の日程などを対象者に知らせる
- 0日定期健康診断を実施する
- 1か月以内結果を本人に通知する
結果を労働基準監督署に提出する
- 3ヶ月以内
(2週間以内が望ましい)健診結果で異常があった人に対する医師等(産業医)の意見を聴く(定期健康診断の個人票に意見を記載してもらう)
- 就業上の措置を決定する
ややこしい条文を沢山引用したわりに、まとめたらこれだけになりました(笑)。
「労働衛生のしおり」によれば、定期健康診断の有所見率は年々増加していて、令和4年は58.5%です。
有所見者が増加するということは、産業医が意見を述べる対象が増えるということです。
はたらく人の高齢化も進んでいるので、産業医が意見を述べる責任も重大です。
ぜひはたらく皆さんには健康になってもらいたいと願っています。
そのためにどうしたらよいか、一緒に考えていけたら嬉しいです。
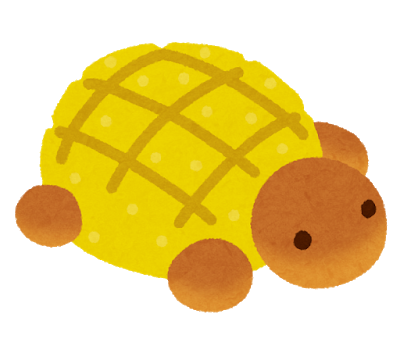
最後までお読みいただきありがとうございました。
またお会いしましょう。