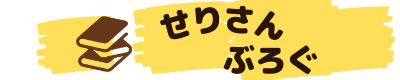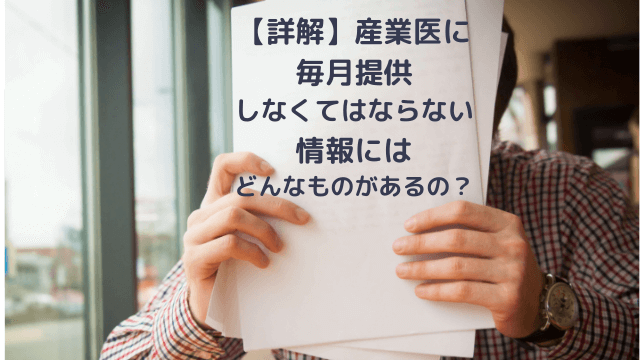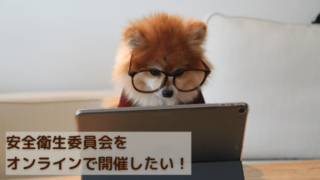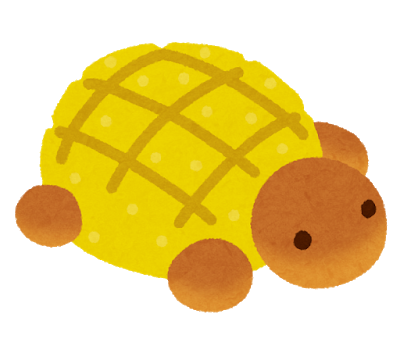
こんにちは!せりです。
産業医が来たら、産業医に必要な情報を提供しなくてはなりません。
でも、必要な情報って何?って思いますよね。
どんな情報を、どのように提供するかは、実は法令で決まっているんです!
できるだけわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
※わかりやすく書きなおしました
産業医に提供しなくてはならない情報一覧
産業医が職場の健康管理を行うためには、職場やそこではたらく人の情報が必要です。
何を提供しなくてはならないかは、平成31年4月施行の改正労働安全衛生法と改正労働安全衛生規則で定められています。
厚生労働省から出ている『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます』 というパンフレット(以下、パンフレット)がわかりやすいので、そちらを貼っておきます(下のバナーをクリックして読めます)が、面倒ならとばして、解説から読んでも大丈夫です。
ア:①健康診断、②長時間労働者に対する面接指導、③ストレスチェックに基づく面接指導実施後 の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨・その理由)
提供時期:①~③の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
イ:時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間(健康管理時間の超過時間))
提供時期:当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。
ウ:労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
提供時期:産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
この厚労省のパンフレットによれば、産業医に提供しなくてはならない情報は大きく分けて3つ。
「ア」「イ」「ウ」と分けられているので、それに沿って解説します。
アの解説
ア:①健康診断、②長時間労働者に対する面接指導、③ストレスチェックに基づく面接指導実施後 の既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨・その理由)
提供時期:①~③の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
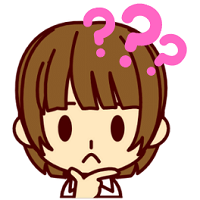
…何言っているのか、わからないのって、わたしだけ?
わからなかったところをリストにしました。
そんな疑問を順番に解説していきます。
産業医に伝えるべき情報はなにか
もとになる条文(最後にまとめてあります。気になる方は目次から飛んでください)で確認したところ、産業医に伝えるべき情報は以下の通りでした。
つまり、健康診断の生データとか、面接指導の結果とかではなく、あくまで措置の内容を知らせるということです。
では、その次の「提供時期:①~③の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること」の、医師又は歯科医師とは誰の事なんでしょうか?そして、意見とは?
医師又は歯科医師の意見とは?
健康診断で異常所見がある人については、事業者は医師又は歯科医師の意見を聴かなくてはならないと法令で定められています。
この「医師又は歯科医師の意見」の内容は、「通常勤務」「就業制限」「要休業」などの就業区分と、それに伴う就業上の措置に関する意見ということです (表1)。
| 就業区分 | 就業上の措置 |
|---|---|
| 通常勤務 | 通常の勤務でよいもの |
| 就業制限 | 労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、 労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、 深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる |
| 要休業 | 休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる |
長時間労働者に対する面接指導やストレスチェックに基づく面接指導でも、面接した医師から就業上の措置に関する意見が出されることがありますので、これも同じように扱います。
医師による就業上の措置に関する意見とは
医師が、健康診断の結果や長時間勤務者・ストレスチェック後面接の結果によって、『この労働者は「通常勤務」でよい』とか『「時間外労働の制限(就業制限)」をした方がよい』など、事業者に意見を述べること。
ややこしいんですが、ここでいう「医師」は、産業医とは限りません。外部の医師でもいいのです。
「遅滞なく」ってどのくらい?
このパンフレットによれば、「遅滞なく」はおおむね1月以内。
ちなみに、「速やかに」はおおむね2週間以内だそうです。
はじめからそう書けばいいのに、と思うのはわたしだけ?
措置とはどういうこと?
ここまでで、健康診断で異常所見がある人や、長時間労働者に対する面接指導やストレスチェックに基づく面接指導を受けた人のうち必要な人には、医師による就業上の措置に関する意見が述べられることがわかりました。
ここまではまだ措置は行われていません。
措置とは、医師による就業上の措置に関する意見を受けて事業者が実際に何を行ったか、ということです。
事業者は、医師や歯科医師の意見を聴かなくてはならないのですが、必ずしもその意見に従わなくてはならないわけではありません。事業所の状態、従業員の意見などを総合的に判断して、実際にできることをします。
つまり、事業者は
労働者について、医師や歯科医師から就業上の措置に関する意見をきく
↓
それを受けてどんな対応をとるか決める
↓
産業医に、何をしたか、またはする予定なのか、あるいは何もしないことにしたのか、という決定とその理由を伝える (就業区分から一カ月以内)
という一連の行動をとることが求められています。
健康診断の結果は見せなくてもいいの?
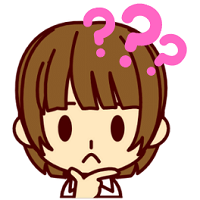
結局、健康診断の結果は産業医に見せなくてもいいってこと?
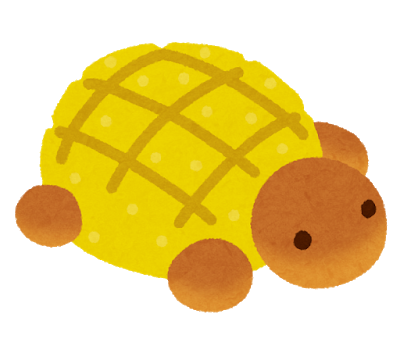
ここだけ見るとそうもとれますが、実際には「結果も見せてほしい」と産業医に言われるのではないでしょうか。
就業上の措置に関する意見は、産業医がいれば産業医に聴くのが望ましいとされています。就業上の措置に関する意見を産業医がするのなら、産業医はもちろん健康診断の結果を見るので問題ありません。
しかし、就業上の措置に関する意見を産業医でない医師が述べている場合、産業医が措置内容だけを報告されて健康診断の結果を見ないということも起こり得ます。
ただ、それでは産業医も情報が少なすぎて困るので、健康診断の結果も見せた方が良いでしょう。
また、どんな措置を講じるかも、実際には産業医と相談しながら決定するのが良いと思います。
イの解説
イ:時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた情報(健康管理時間の超過時間))
そのほかに産業医に渡さなくてはならない情報は、
時間外・休日労働時間が1月あたり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報です。
これは、「当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること」とされています。
1か月間の時間外・休日労働時間は、毎月1回以上、一定の期日を決めて算定するよう定められています。算定を行った後、「速やかに」、つまり2週間以内に産業医に情報提供しなくてはならないということです。
産業医が毎月決まった日に事業場に来るのなら、産業医の訪問日から逆算して2週間以内に時間外労働の算定日を設定すれば、産業医が訪問した日に渡せばよいので楽です。(後述するように、メール等で訪問日以外に提供するという手もあります)
もし、80時間を超える時間外勤務をした労働者がいなかったら、「いない」という情報を忘れずに提供しましょう。
ウの解説
最後の項目は、
ウ:労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
なんだか漠然としていますが、パンフレットには例として
- 労働者の作業環境
- 労働時間
- 作業態様
- 作業負荷の状況
- 深夜業等の回数・時間数
があげられています。
必要な情報が何か、ということは事業者と産業医であらかじめ決めておくのが良いでしょう。
提供時期は、「産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること」ですので、おおむね2週間以内です。
情報はどのように渡したらよい?
これは、パンフレットをそのままご紹介しましょう。
紙で渡してもUSBで渡しても、メールで送ってもよいという自由度の高さ!
文書の保存に関しては、デジタル保存してもよい文書をいちいち指定していたことを考えると、とてもゆるいです(記事:「健診結果や産業医の面接記録をデジタル保存してもよい?」参照)。
オンラインで安全衛生委員会を開催する場合にも助かりますね!
産業医への情報提供→安全衛生委員会を効率化する方法
一番簡単な方法は、前述したこのパターンです。
- 産業医の訪問日から逆算して2週間以内にひと月の時間外労働時間の算定日を設定
- 産業医に提供すべき情報は産業医に渡し、そこから個人情報を抜いたものを安全衛生委員会の資料として使用
- それをもとに安全衛生委員会を運営
資料作りの手間と産業医の所要時間を極限までスリム化できます。
(繰り返しになりますが、安全衛生委員会用の資料からは、承認されていない個人情報は忘れずに抜きましょう!)
関連法令
- 労働安全衛生法 第13条第4項、第13条の2第2項
- 労働安全衛生規則 第14条の2第1項、第2項、第15条の2第3項
第13条4項 (産業医等)
産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間 に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
第13条の2第2項
前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者につ いて準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
第14条の2第1項、第2項
一 法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
二 第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が 一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
2 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
二 前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七 の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
三 前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
第15条の2第3項
第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。
まとめ
産業医に提供しなくてはならない情報と、その方法について解説しました。
提供しなくてはならない情報は以下の通りです。
①~③については医師・歯科医師から就業区分の判定を受けたら1か月以内に、④~⑤についてはその月の算定が終わってから2週間以内に、産業医に情報を提供しなくてはなりません。
提供方法は、紙でも電子媒体でもメールでもオッケーです。
ただし、どんな情報を提供したかは記録・保存しておくことが望ましいです。
こうしてみると、毎月なんらかの情報を産業医に提供しなくてはならないことになります。
何もない時でも、長時間勤務者はいない、という情報を提供することになっているからです。
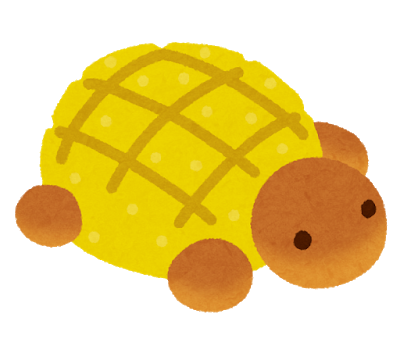
産業医の権限が強化されるにつれて、産業医の業務も増えていますが、それをサポートする職場の方々の業務も増えています。
必要なポイントは確実におさえつつ、効率的に進めていくことが産業保健のレベルアップにもつながると思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!