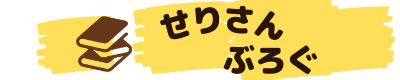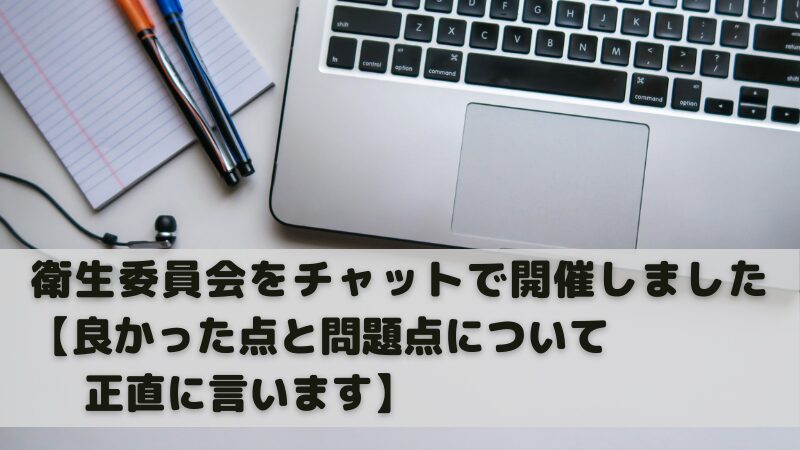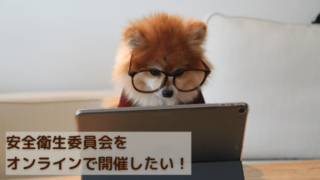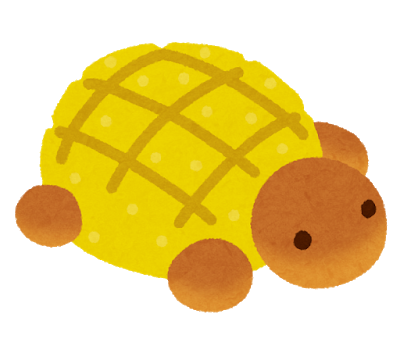
こんにちは!せりです。
以前、安全衛生委員会をオンラインで開催する方法についてお伝えしましたが、
(安全衛生委員会をオンラインで開催したい!【開催方法、根拠法令等を徹底解説】)
私の職場でも1年間、実際にチャット形式で衛生委員会を開催してみました。
正直に言えば残念な感じになってしまいましたが、この記事ではその経緯と良かった点、問題点についてお話しします。
衛生委員会をオンラインで開催しようと考えた経緯
毎月開催が法令で定められている衛生委員会。
構成メンバーも法令で定められていることから融通がきかず、なかなか出席者が揃わないことから私の職場でも毎月開催は難しい状況にありました。
しかし、いくら危険の少ない事務職場とはいえ、まじめにやろうと思えば議題はそれなりにあります。
そこで、衛生委員会をオンラインで開催できることを紹介し、とにかく確実に毎月開催しようと担当者に声を掛けました。
チャットに決まった理由
安全衛生委員会をオンラインで行うことについて、「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全衛生委員会等の開催について(令和2年8月27日 基発0827号 厚生労働省労働基準局長 通知)」では、以下の方法があげられています。
- 映像と音声を伴うオンラインの会議
- 音声だけの会議
- チャットによる会議
- 電子メールなど 即時性のない会議
一つ一つ検討した結果、
✖ オンライン会議、音声だけの会議 →衛生委員会のメンバーは同じ建物内に勤務しており、会議場に出向くことはそれほど大変ではない。一方、オンライン会議であっても、日時を合わせたり会議中拘束されたりすることは同じ。つまり、変更するメリットがない。
✖ 電子メール →メーリングリスト型式にしても、メンバーの意見を確実に時系列順に並べえることは難しい。やりとりが多くなるとメールが長くなり読みにくい。
○ チャット →職場のイントラにチャット機能がついており、簡単に始められる。意見が時系列順に並び、見やすい。追加の資料も出しやすく、見やすい。
ということでチャットで行うことになりました。
運用方法
- メンバー及び事務局限定のチャットルームを作成
- 毎月第○月曜日から金曜日までを開催期間とする
- 資料は開催前に送付される
- 開催期間中にチャットで意見を述べる
先に紹介した通達ではチャットを即時性のあるツールと位置付けていましたが、私の職場の運用ではむしろメールに近い形です。開催期間中ずっとチャットルームを見ているわけではないので、必ずしも即時性はありません。
良かった点
- 開催期間が長いので、必ず参加できる
- 資料を見てじっくり考える時間がある
- 難しい機械の操作もいらず、声も出さないので自分のデスクから参加できる。
- 議事録を作るのが簡単
問題点
- 通達にも留意点としてあげられていたが、意見表明のないメンバーがおり、資料の確認状況や意見提出の意思を確認する手間がかかった
- そもそも意見が出づらかった
衛生委員会の雰囲気は職場によって違うと聞いたことがありますが、私の職場の衛生委員会は「和をもって尊しとする」タイプでした。
実際に集まる対面会議や映像を伴う会議と違い、チャットでは周囲の空気を読むことができないため、初めから確たる意見がある場合以外は意見をだしづらいようでした。
そして、実際には衛生委員会のメンバーも普通の業務に忙殺されているわけで、職場の衛生についてそれほど意見を持つこともないようでした(まあ、わかります)。
そうなると、意見表明はほとんどなく、事務局に促されて各メンバーから「特に意見なし」と打ち込まれ、期間がすぎて閉会、ということが繰り返されてしまいました。
そのうち、意見交換どころか意見自体がないので、皆さんあまりルームを開かなくなったのか事務局からの連絡にも返信がない始末。
こんなはずでは…。
正直に言えば、これまでの衛生委員会も事務局が提案した事項が会議の前に根回しされ、会議では少し質問が出た後に承認されるのが常でしたので、質問の時間がなくなった分時短になって効率的になったとも言えます。
しかし、(時々的外れなこともあったにしても)質問をして回答を聞くことはメンバーの職場の衛生に関しての理解をわずかにでも深める効果があったかもしれないと考えると、現状としては後退していると言わざるをえない、残念な事態になってしまいました。
今後のための提案
- 委員会の開催期間を1週間から3日間に短縮する
- 委員会開催中は1日1回はチャットルームを見ることとする
- 1人最低1回は発言する(資料を確認したこと、それについての意見など)
- 年度初めと秋の年2回は対面会議にする
- これまでは議事録として発言のすべてを公表していたが、公表するのは「議事の概要」とする(発言のハードルを下げる)
もしくは、すべてリセットして
- これまで通り対面会議だけにする
…難しい問題です。
会議のための時間が設定されると、少なくともその時間は資料を読んだり考えたりします。
しかし、それがなくなると資料を読んだり考えたりする時間を自分で捻出しなくてはなりません。
職場の衛生について考えることが本業ならともかく、それ以外のメンバーには負担が大きかったのではないかと思われました。
まとめ
衛生委員会をチャットで開催しました。
運用方法
- 期間は1週間。メンバー限定のチャットルームを開設する
- 必ずしも即時性のない方法(常時張り付いているわけではない)
結果
- チャットルームが過疎ってしまい、意見が出ずに終わってしまうことが多かった
- 現状では成功したとは言い難い。
- 今後チャット形式を継続するかどうかも含めて検討が必要
衛生委員会の活性化については、産業医向けの書籍などでもよく取り上げられている話題です。
裏を返せば、みんな活性化しなくて困っているということで、自分のところだけではないと思うと慰められますが、そんなことを言っている場合ではありません。
いろいろと試してみてまた後日談をお話しできたらと思います。
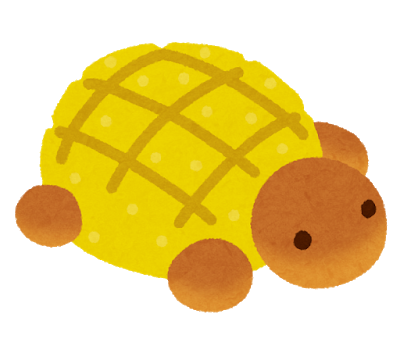
最後までお読みいただきありがとうございました。
またお会いしましょう。