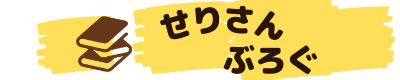※わかりやすく書き直しました
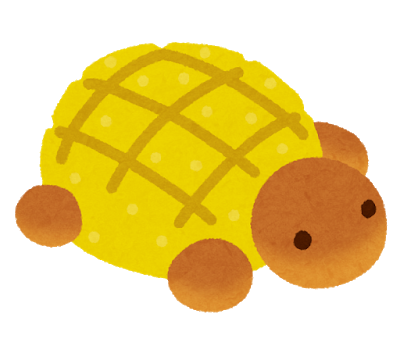
こんにちは!せりです。
新型コロナウィルス感染症の流行以降、オンラインでの会議もすっかり定着しました。
安全衛生委員会もオンラインで開催したいと考えている方もいるでしょう。
結論から言えばそれは可能ですが、いくつか留意すべき事項があります。
この記事では、オンラインでの安全衛生委員会の開催方法、根拠法令等をできるだけわかりやすく、徹底解説します。
常時50人以上の労働者を使用している事業場では、衛生委員会の設置が義務付けられていますが、時々こんな相談を受けることがあります。

安全衛生委員会ですが、テレワークの人もいて…毎月開催はメンバーがそろわなくて難しいです。
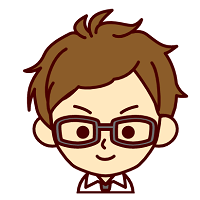
社内の会議はオンライン開催が多くなりました。
安全衛生委員会もオンラインで開催したいのですが、できませんか?
結論から言えば、
安全衛生委員会はオンラインで開催できます。
しかも、
・映像を伴う通常のオンライン会議
・音声だけの会議
・チャット
・メーリングリスト
で行うこともできます。
しかしながら、オンライン開催には、通達に書かれた要件を確認しておく必要があります。詳しく見ていきましょう。
安全衛生委員会をオンラインで開催するための要件
安全衛生委員会をオンラインで開催するためには、使用する情報機器と委員会の運営について以下の通達に書かれた要件を確認しておく必要があります。
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全衛生委員会等の開催について(令和2年8月27日 基発0827号 厚生労働省労働基準局長 通知)
労働安全衛生法
第17条(安全委員会)
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第18条(衛生委員会)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を
述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
第19条(安全衛生委員会)
事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない
ときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする
使用する情報機器について必ず満たすべき3つの要件
運営上、満たすべき要件
即時やりとりができれば、映像がない音声通信やチャットで開催してもよい
(ただし、必要な資料が確認できること、調査審議がきちんと行えることが不可欠)
さらに、即時やり取りができることが原則ではありますが、以下の要件を満たせば電子メールなど、即時性のない方法で行うこともできます。
電子メールなど 即時性のない方法で安全衛生委員会等を開催する方法
電子メールなどの即時性のない方法で行うための条件は、安全衛生委員会等で了承されていること、
以下の4つの留意点に気を付けることです。
・電子メールなどの即時性のない方法で行うためには、安全衛生委員会等で了承されていることが必要。
・スムーズに意見交換や調査審議が行えるよう、資料をメンバーに余裕をもって送付すること、他のメンバーの質問や意見、議論の経緯がわかるようにすること、意見調整役の担当者を決めることが必要。
まとめ
安全衛生委員会等をオンラインで開催するためには
「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全衛生委員会等の開催について」(令和2年)に書かれた以下のポイントを確認する必要があります。
テレワークやオンライン会議の体制が整っているところなら、すでに必要な要件を満たしているところが大部分ではないかと思います。
また、チャットやメーリングリストを使って開催することもできますから、メンバーが揃わなくて開催できない、という状況はかなり減るのではないかと考えます。
試しに一度、安全衛生委員会をオンラインで開催してみてはいかがでしょうか。
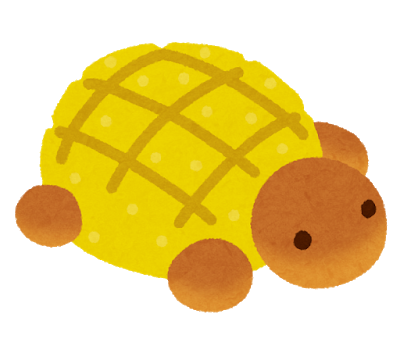
最後までお読みいただきありがとうございました。
またお会いしましょう。